|
|
|
 プロフィール プロフィール
1938年大阪府生まれ。大阪大学法学部卒。山一證券取締役営業企画部長、取締役企業開発部長を経て、1987年、M&A専門会社、株式会社レコフ(注1)を設立、代表取締役に就任。1995年M&A専門月刊誌「マール」創刊。2008年、同社代表取締役を退任。レコフグループ
代表に就任。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
片岡:
|
今月の右脳インタビューは吉田
允昭さんです。吉田さんは銀行や証券会社が本業に付帯するサービスの一環として行われていたM&A業務を、日本で初めてフィー・ビジネス化、その後、数多くのM&Aを手掛け、また業界の発展を支えてこられました。
|
|
吉田:
|
私がM&Aをビジネスとして始めたのは1970年前後で、1973年には山一證券にM&A部隊を作りました。実は米国でM&Aビジネスが始まったのも、ほぼ同時でした。Morgan
StanleyとFirst BostonがM&Aをビジネス化、前後してLehman
Brothersも参入、同社が定めたフィーの料率がLehman Formula(注2)として広まりました。米国人は企業を売ることを害悪と考えません。そうしたカルチャーの違いから、日本よりも遥かに大きな企業売買のマーケットがあって、市場のテクニック、TOB(takeover
bid)やMBO(management
buyout)等の開発が進みました。1980年代前半になるとLBO(leveraged
buyout)を用い、企業が金融商品化しました。KKR(注3)を創業し(1976年)、LBOを確立したJerome
Kohlberg, Jr., Henry Kravis, George R.
Robertsの3人は「企業を金融商品化するためにLBOを創ったのではなく、M&Aで企業を伸ばすためだったのに、とんでもない方向に動いている」と嘆いていました…。その後、Michael
Robert Milkenのジャンク債が続きます。また1985年には元商務長官のPeter G.
PetersonがBlackstone(注4)を立ち上げM&Aビジネスを10人程で始めました。これがM&Aブティックの始まりです。
|
|
片岡:
|
同社は今では世界最大級のファンドとなっていますね。
|
|
吉田:
|
このビジネスは情報が一手に集まりますので、多くのM&Aブティックがファンドとなっていきました。私は、それは亜流だと思います。M&Aは企業を大きくするために、良くするために、脳神経外科のような技術を使って行うのが神髄だと思うからです。一方、日本では1974年に施行された大規模小売店舗法(注5)がM&Aマーケットを作ったと言っても過言ではありません。大店法で500平米以上の店舗の出店に厳しい条件が課され、100億、200億といった売上のスーパーマケットでは出店が難しくなりました。これらの企業等が売り物化し、既に上場しファイナンス力を付けてきていたジャスコ、ダイエー、イトーヨーカ堂、ユニーの4社が買い手の中心となって再編が進みました。
|
|
片岡:
|
政策的にM&Aを育成する意図があったのでしょうか。
|
|
吉田:
|
当時、政府は勿論、普通の経営者も「M&A」という言葉さえ知らないという状況でしたので、大店法は結果として役立ったということだと思います。1980年代中頃になって、経済企画庁の藤岡文七(現
内閣府審議官)(注6)が官僚として初めてM&Aの重要性を取り上げました。
|
|
片岡:
|
収益はどのような形で計上していたのですか。
|
|
吉田:
|
証券会社は免許業種です。山一證券の経営陣は当初、M&Aビジネスが証券の付随業務に該当するのかどうかを大蔵省に尋ねることすら怖がって、M&Aの部署を作らず、最初は本店営業部営業三課においてM&A業務を行い、1980年からは引受本部内の引受本部付という部署で行って、その他収入として計上していました。その後、大蔵省大臣官房審議官だった藤田恒郎(注7)が経済雑誌のインタビューで「M&Aは堂々たる証券業務である」と述べ、そしてM&Aは金融緩和によって大きな伸びを見せます。余剰資金が内需拡大、土地と株に回り、それでも余って海外の企業買収に向いました。その殆どはビル等の不動産を買収する財テク型M&Aで、結果的に日本企業は多額の損失を抱え、全体で二十兆円近くを失いました。その次にM&Aが伸びるのは規制緩和によるもので、中小企業から始まり、大企業が参入、法律の改正も進みます。特に独禁法の改正は大きなインパクトがありました。そしてグローバリゼーションです。その最たる例がサントリーとキリンです。2050年には人口が1億を下回るとも言われていますが、購買力人口はその10倍のスピードで落ちていきます。だから1位と組んで絶対的なシェアを維持していないと海外には打って出られない…。これはどんなマーケットでも同じです。このため国内での再編のためのIn-Inの買収と、国内で圧倒的なシェアを持った企業が海外での買収に乗り出すIn-Outの買収が同時並行的に大型化して進みます。
|
|
片岡:
|
御社は欧米型のアドバイザーとは一線を画すM&Aサービスを行っていますね。
|
|
吉田:
|
欧米の場合は、どちらか一方のアドバイザーとなり、それぞれのアドバイザー同士が話し合うというスタイルを取ります。しかし日本流のM&Aというのは仲人のように、二社の間に立って仲介し、フェアなジャッジメントをして、両社に信頼をされながらM&Aを創り上げていく作業で、両社のカルチャーや心を十分理解をして紡ぎ合わせていくものです。会社のカルチャーを見極めることが大切ですから、私は非常に早い段階で両トップ同士の面談を設定します。社長を見れば会社のカルチャーや哲学が分かり、後はテクニカルな問題です。互いの問題点も分かりますし、メディアや組合、或いは公取にどのように対応していくかといったことも同じ悩みとして乗り越えることが出来ます。互いのメンツが問題となることもありますが、それを解消するような提案を仲人が行うことも必要です。また従業員一人一人を見ると「合併すれば経理部長は一人になる、この人や家族の人生はどうなるのだろう…」と、それは真剣な気持ちになり、そこに心が通います。であれば合併後1年間は経理を2つ置くといった取り決めを最初の段階で行うことも出来ます。従業員や取引先の心をくみ取り、痛みを感じることが出来なかったらM&Aの仲介はできません。私には企業の鼓動、悲しみ、喜びが聞こえます。それはとりもなおさず、社長の鼓動です。勿論、社長の鼓動と企業の鼓動が異なることもあります。彼はここのトップになるべきではなかった…。自分のことだけを考えている…。これは見極めないといけませんが、それには数多くのディールをこなすしかありません。そして仲人は黒子として触媒に徹し、消えてなくなるべきものです。M&Aは両トップが決断しないことには成立しませんし、その後の苦労を背負うのも彼らです。10年ぐらいたって、企業の成長した姿を見て「良かった」とただ一人で思うのがM&Aマンの無上の喜びです。
|
|
片岡: |
仲人という手法は欧米のビジネス・カルチャーからするとなかなか理解し難い部分もありますね。
|
|
吉田:
|
利益相反を生みかねないという人もいますが、そんなことはありません。日本には日本の風土に合ったやり方があります。そして今後、成長が続くアジアはまさに日本の風土に近いと思います。またアドバイザーが利益相反していたケースもあります。日本のある大手企業が米国企業を買収した折に、アドバイザー間に水面下で不透明な取引があり、日本企業は1000億円単位の損害を被った可能性もあるという指摘があります。また世界有数の広告代理店のCEOから日本の広告代理店を買収したいという相談を受けた時には、彼は仲人というやり方をどうしても理解できませんでしたが、「Mr.
Yosidaがそこまでいうのなら」と任せてくれました。買収が上手く行って、調印式の後の宴席で「これまで何百もの買収を手掛け、幾つもの投資銀行を使ったが、レコフのやり方は、その何れに勝るとも劣らない。このやり方こそ正しかった」と言ってくれました。
|
|
片岡: |
アドバイザー方式には、どういった難しさがあるのでしょうか。
|
|
吉田:
|
ある国内の大手メーカー同士の合併では、当初トップ間での合意が成立していました。ところが基本合意から本契約を結ぶまでに1年程かかります。彼らはそれぞれアドバイザーを付けていました。基本合意後、一方の会社が、今後こういうことをやる、ああいうことをやると次々に発表を続けました。当初はこの会社の株価は低かったのですが、そのうちに逆転し相手よりも高くなり、相手のトップは不信感を募らせました。これが仲人であれば双方のトップに「こうしたほうが良い…」と言えますが、アドバイザーではそうしたことはなかなか難しく、結局、合併に至れず、目的を達成できませんでした。勿論、欧米流のやり方が適しているケースも当然あり、それぞれに役割分担があります。
|
|
片岡: |
例えばどういったケースでしょうか。
|
|
吉田:
|
破綻寸前の売り手に頼まれた時、つまり少しでも高く売って欲しいと頼まれた場合等はアドバイザーが適していて、「この指とまれ」的にオープンに募集しないとなかなか良い相手が得られません。弊社の新社長(注8)はメリルリンチ出身で、こうした業務も手掛けていきたいという気持ちがあり、社内でも葛藤が起きているようです。メリルリンチの様な大きな会社であれば世界中から沢山の情報が入ってきますので特に「この指とまれ」的な手法が良いと思います。そういう新しいカルチャーも入れていかないといけないので、あえて起用しました。だから葛藤が起こり、それを乗り越えないといけません。仲介をやっていた人間がアドバイザーのやり方を見て、或いはアドバイザーをやっていた人間が仲介を見て、より良い会社になっていくであろうというのは理想論ですが…。
|
|
片岡: |
それでも常にやっていかないといけない…。
|
|
吉田:
|
そうです。だからあえてやれやれ…と。そしてその為に私は聊かも経営にタッチしません。ところでM&Aの会社というのは職人の集合体です。レコフという会社は社員に最低の保証と無限大の活動費を与えるだけで、そこに司令塔はありません。経営者は全体を見ているだけで、各々の生産性の主体は個人です。私は経営からは引退をしましたが、M&Aのマーケットからは引退しません。ネットワークが必要ですし、それに頼まれたらノーとは言えません。
|
|
片岡: |
貴重なお話を有難うございました。
|
|
|
〜完〜(敬称略) |
|
|
|
|
インタビュー後記
吉田さんは企業のM&Aを手掛ける傍ら、M&Aの手法を用いて国と国との良いパートナーシップ作りに取り組んでいます。日本は少子化で今後巨大な需給ギャップが生じ、新しいマーケットの開発を必要としています。それにはベトナムが最適で、ベトナムは人口8600万人、平均年齢26歳と、ちょうど昭和30年前後の日本に近く、この市場を開発すれば、同じ成長を今後50年間、共に歩んでいくことが出来るそうです。今後、まさに「仲人」の真骨頂が発揮されます。吉田さんの趣味は、源流を求めて川を登ることだそうですが、まだまだ多忙な日々は続きそうです。
|
|
|
|
聞き手
片岡 秀太郎
1970年 長崎県生まれ。東京大学工学部卒、大学院修士課程修了。博士課程に在学中、アメリカズカップ・ニッポンチャレンジチームのプロジェクトへの参加を経て、海を愛する夢多き起業家や企業買収家と出会い、その大航海魂に魅せられ起業家を志し、知財問屋
片岡秀太郎商店を設立。 |
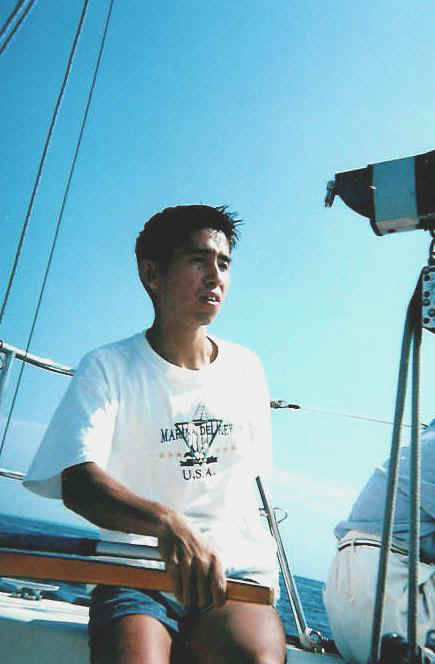 |
|
|
|
|
|
脚注
|
|
|
注1 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://www.recof.co.jp/ (公式ページ)
|
|
注2 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Formula (wikipedia)
|
|
注3 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://www.kkr.com/ (公式ページ)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kohlberg_Kravis_Roberts (wikipedia)
|
|
注4 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://www.blackstone.com/(公式ページ)
|
|
注5 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/大規模小売店舗法 (Wikipedia)
|
|
注6 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/藤田恒郎 (Wikipedia)
|
|
注7 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/藤岡文七(Wikipedia)
|
|
注8 |
詳細は、下記をご参照下さい。
http://www.recof.co.jp/about/p_greeting.html
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
片岡秀太郎の右脳インタビューへ |