| |
| |
|
プロフィール
1940年福岡県生れ。九州大学経済学部を卒業後、アサヒビール株式会社入社。代表取締役社長兼COO、代表取締役会長兼CEOを歴任。現在、アサヒグループホールディングス株式会社 相談役。
|
 |
|
|
片岡:
|
今月の右脳インタビューはアサヒグループホールディングス株式会社 相談役の池田弘一さんです。それでは入社なさった頃の様子などお聞きしながらインタビューを始めたいと思います。
|
|
池田:
|
私が入社した頃、アサヒビールのシェアは落ち続けていました。アサヒビールの母体は大日本麦酒といい、戦前はシェアが75%、残りを麒麟麦酒(現キリンビール)が占め、両社で市場をほぼ独占していました。戦後になると両社は集排法による分割の対象となり、最終的に大日本麦酒だけが朝日麦酒(現アサヒビール)と日本麦酒(現サッポロビール)に分割されました。もともと大日本麦酒はいろいろな会社が合併してできた会社でブランドを複数持ち、それごとに地盤、工場を持っており、分割に伴って概ね朝日麦酒が東京から以西、日本麦酒が以東を引き継ぎました。将来は一緒になるつもりだったのだと思います。この分割によって朝日麦酒がシェアトップ、その後が日本麦酒、麒麟麦酒となりました。しかし麒麟麦酒はシェアが低くても全国ブランド、一方、朝日麦酒は東京のお客さんには馴染がなく、日本麦酒は大阪のお客さんにとっては馴染がない…。更に朝日麦酒、日本麦酒はもともと同じ会社だったので相手の手の内が全てわかっていました。このため麒麟麦酒は漁夫の利を得たような面があります。またビールは元々高級品で殆どの需要は業務用、つまりお店で飲むビールだったのですが、高度成長とともに大衆化してくると、麒麟麦酒はいち早く家庭用市場に力を入れ、設備投資も強烈に進めて生産力を増強しました。しかし我々は業務用に強かったので手間がかかる家庭用にはあまり力を入れず、生産力強化にも後れを取りました。
更に1966年、社長の山本爲三郎氏が急逝します。強力なリーダーシップを発揮した経営者だっただけに後継体制も整っておらず、だんだんリズムが悪くなっていきました。そうなると更に悪化する原因は枚挙に暇がなくなります。勿論、当時の経営者も立て直しに向け様々な手を打ちましたが、狂いだした歯車はとまらず、社内も纏まらない…。そこで社内の結束を図るために、1971年、大日本麦酒の最後の社長で財界の大物だった高橋龍太郎氏の長男で、当時住友銀行の副頭取をしていた高橋吉隆氏を社長として迎えました。高橋氏はマーケティング指向的で「美味しいビールを美味しい状態で消費者に届けよう」というスローガンを掲げました。美味しい状態で…というのは当時のメーカーとしては考えもしなかったことです。そうは言っても立て直しは難しく、その後も赤字になることはなかったのですが、マーケットシェアはどんどん下がり、1985年頃には10%を切るようになっていったのです。
|
|
片岡:
|
転機となったのは?
|
|
池田:
|
1982年、村井勉氏が社長に就任し、QCとCIを導入しました。その際、200人ほどいる管理職全員を集めてQCの勉強会を何度も開いたのですが、これが会社全体で危機感を共有する機会にもなり求心力が生れてきました。また1985年には東京・大阪で5000人という大規模の消費者調査を業界で初めて行いました。他の業界でもこれほど大々的に行ったところはないと思います。その結果、当時一番売れていた麒麟麦酒にも消費者は満足していないという事がわかりました。こうして生れたのが【アサヒ生ビール】(通称コクキレビール)です。1986年に社長に就任した樋口廣太郎氏は新鮮なビールを飲んでもらうために、製造後3カ月以上たった市中の在庫を回収しました。実際にやってみると想定の10倍くらい返品がありました。というのは新しいものに換えてくれるとなると家にあるものまで持ってきた人もいたようで…。また街頭での100万人大試飲キャンペーンや全国2万店を目標とした酒販店店頭での試飲会等も行いました。これは自分たちの新商品が実際に売れていくことを目にした社員にとってはとても自信となったようです。勿論、お店にも、お客様にも伝わります。こうしてシェアも上昇に転じました。
そうした中、商品開発の担当者が「コクがあるのにキレがある」よりも更に先鋭的なところに可能性があるのではないかといってきました。経営陣としては折角、将来をかけて開発した商品がうまく行っているのに、その翌年に新商品を投入するのは…と決断できなかったのですが、やっと首都圏での小スケールで 試験的販売を開始しました。これが【スーパードライ】です。物凄く売れ、1年分の注文が1カ月で来て…。随分、品物も切らしてしましたが、順回転で、お客さんに出来たてのビールが手元に届きました。当然、他社も翌年、同じような商品を出し、所謂ドライ戦争がはじまります。
|
|
片岡:
|
なぜスーパードライは勝ち続けることができたのでしょうか。
|
|
池田:
|
商品としてもお客様が認知するだけの味の差があったのでしょう。それと同時に、設備が少ないところに売れに売れましたので、他の商品を作る余裕がなくなり、売れていたアサヒ生ビールも飲食店用の樽生を除きすべてスーパードライにかえ、米クワーズのライセンス生産用のタンクも転用しました。こうして製造をスーパードライ一本に絞り、品薄ながらも安定的に出荷しました。ところが他社は主力ビールと併行してドライを生産しましたので供給がどうしても不安定となり、この結果生産競争にも勝利したのです。アサヒがスーパードライを出していた時はアサヒの愛飲者プラス・アルファなのですが、各社がドライを出すと、例えばキリンを飲んでいる人もキリンのドライと話題のスーパードライを飲み比べようとなります。これが大きかった…。
|
|
片岡:
|
急成長には当然、代償もありますね。
|
|
池田:
|
急成長を支えるために1987年からの6年間だけでも6000億円近くの設備投資を行い、そのため4800億円に及ぶ社債を発行、1992年には有利子負債が1兆4000億円に膨む…と財務体質が悪化します。1992年、社長に就任した瀬戸雄三氏は売上拡大と効率化を掲げました。勿論、効率化は借金を減らすことです。またスーパードライが売れている間に色々な商品を売ろうと、手を拡げ過ぎていましたので、もう一度スーパードライに力を集中させます。また「鮮度」とともに「廃棄物ゼロ」という目標を設定し、実際にモデル工場であった茨城工場では廃棄物ゼロを達成しました。この二つをTV広告に使い、大変な反響を得ました。更に全国3000人のマーケティングスタッフが古いビールがあれば回収し、商品が前に出ていなければ前に出す…そういったことを行い、半年もするとスーパードライにまた勢いが戻ってきったのです。
そうして1998年、ビール市場でシェアトップとなります。そんな中、今度は発泡酒が出てきました。サントリー、サッポロが先行、続いてキリンも参入、2001年には弊社も発泡酒を発売、発泡酒も含めた市場でNO.1を目指します。そのためにもスーパードライを更に成長させようと、鮮度をより追求、2週間ほどかかっていた製造から出荷までの時間を、まず10日を切れと、それができると5日、3日…と目標を短縮していき、概ね他社の半分になっています。さて、国内のビール市場は1994年がピークで、それ以降はマイナス成長でしたが、アサヒビールだけはスーパードライがあったので、国内市場の中でも成長を続け2001年がピークとなりました。
|
|
片岡:
|
池田さんが社長に就任するのもその頃ですね。
|
|
池田:
|
2002年に社長に就任しましたが、収縮が続くビールの国内市場では、これ以上再成長をさせることはすぐにはできませんでした。
弊社には「社長への手紙」という社員ならば誰でも社長に手紙を出せる仕組みがあったのですが、これが実際には機能していませんでした。そこでこれを機能させるために、最初のビデオ朝礼で元気の出る手紙を送って欲しいと全社員にお願いしたのです。そうすると2週間で3000通くらいの手紙が届きました。勿論、職制の命令もあったものと思いますが、それでも3000通も集まったのは嬉しかった…。ある工場からの手紙の中に修繕費が足りないというものがあり、名前を伏せて工場長に問い合わせると、わずかでも予算を増やしているといいます。ではどう配給しているのか尋ねると、万一の事があるかもしれないので予備費を少しとって課長に渡している、更に課長に聞くと同じように予備費を取って班長に配給しており、班長も同じで予備費をとって…と答えます。皆まじめなのですが、結果的に現場に届いていませんでした。
またNO.1になるという最大の夢を達成し、その後に何をすればいいのか、アサヒビールは何処に向かうのか、方向を見失っていました。そこで3カ年計画で「連結とグローバル」を目標に掲げたのです。全ての子会社を利益で評価していましたが、バックオフィス系の会社はコストを多めに請求し、余ったら利益となります。これはおかしい。そこで事業系と事業支援系を分けて事業会社は事業の拡大を指標とし、事業支援会社はコストダウンで評価しました。そうして無駄な会社は売却、或いは吸収させたのです。かつて弊社は売上が伸びても利益は低く、2000年には赤字決算をしてバブルの清算を行っています。その後、改革を続け、体質も改善し、9年連続増益を続けています。
そして2004年には中国最大手の食品グループの康師傅控股有限公司(英文名称:Tingyi Holding
Corporation)と合弁事業を始めました。これは奇跡的な交渉で、伊藤忠の紹介で10月に会い、年末には合意して年が明けた1月の終わりに発表しました。この合弁会社は昨年、中国のコカコーラを抜いて中国NO.1の飲料会社となり(出典:Canadean)、弊社にとっては持分法適用関連会社で連結の対象となりませんが100億円単位で貢献してくれています。また中国ではビール会社を地域ごとに4社ほど経営していたのですが、ナショナルブランド化が進展して地域会社では競争に勝てなくなり赤字を出していました。そこで2009年、合弁会社を一緒に行っていた青島啤酒有限公司(青島ビール)の株式を、19.99%を593億円で取得、ここを中心に中国でのビール事業を再編しています。この時はアンハイザー・ブッシュ・インベブ(ベルギー)が所有していた株を買い取りました。インベブ(ベルギー)がアンハイザー・ブッシュ(米)を買収した(注1)ところにリーマン・ショックが起こりましたので、苦しくなって同社の放出するのではないかと、こちらから働きかけ、私もベルギーに行きました。本当はもう少しシェアが欲しかったのですが中国当局が許してくれませんでした。こうしてビールと飲料については大きな基盤を作ってきたのです。但し、持分法適用関連会社では売上には入ってきませんので豪の飲料会社は100%買収しました。英のキャドバリーグループという菓子メーカーが飲料事業(シュウェップス)を売りに出すという情報が入り、あるアドバイザーの紹介で具体化する前に会いに行き米や欧の事業には興味ないが豪に興味がある事を伝えると豪の事業はスケールが小さいのでまだスケジュールに入れていないということでした。「我々はこれくらいの腹積もりにしているからビットになる前に知らせて欲しい」と伝えました。翌年になって「あの約束はまだ生きているか」と連絡があり、具体的に話を進めて2009年、同グループの豪における飲料事業(シュウェップス・オーストラリア)を約758億円で買収しました。
|
|
片岡:
|
彼らはなぜビットに出してこなかったのでしょうか。少しでも高く売りたいはずですが。
|
|
池田:
|
それは米欧での売却に忙しく規模の小さい豪まで手が回らないという面もありましたが、こちらも「ビットしてもここまでの金額は出ないはずだ」と伝えていました。会社は買えても人が分散してしまっては困ります。我々が直ぐに経営できるものではありません。ですから「会社の評価には人が入っている、それを確保して欲しい。ビットにするとそれが分散してしまう恐れがある。そこを確約してくれたらこの金額をだす…」といい、現実に全員が残ってくれたのです。勿論、当方の要望として、これ以上の社員は要らないという上限もつけました。
|
|
片岡:
|
御社に比べて規模の小さい企業を買収するケースが多いようですが、より大規模なM&Aについてはどのようにお考えでしょうか。
|
|
池田:
|
M&Aは資本の論理で利益を拡大しようとします。日本流の経営かもしれませんが、持続的な成長が、株主を含めたステークホルダーに対する我々の約束ですし、また飲料はその国の歴史と文化の上に成り立つものです。例えば中国でのビール事業で苦戦したのは価格だけでなく味覚の差もありました。同じ甘い、苦い、辛いでも国によって違い、中国人にとって苦いという表現は不味いという意味になってしまいます。こうしたことが積み重なります。ですから康師傅控股有限公司のトップも「中国でビジネスをするのだったら我々のような台湾人と組むのが良い、我々であれば中国語も話すし、日本人の考え方もわかる。何よりも味について中国と親和性がある」とアピールしていましたし、現実に私もそう思います。そこで我々は生産管理等を提供し、実際の開発や営業は彼らが行っています。先ほどのシュウェップスの時も経営陣を残すように依頼しました。
こういう視点から見ると大きなスケールのM&Aは短期的には利益が上るかもしれませんが、永続的な成長をさせるという意味ではまだ自信が持てません。また私が経営していたときにはキャッシュフローが3年間で4000億円程度、M&A資金は2000億円、残りは財務体質の強化と株主還元にしていましたので財務的にも難しい面がありました。今はキャッシュフローも増え、財務体質も強くなっていますので、現経営陣はもう少し思い切ってやれると思いますが、欧米のように負債を大きく増やしてM&Aをすることが、日本の会社にとっても良い事かどうかは見極めていく必要があります。
またこの規模の戦いはビール業界の場合は勝負がついてしまっていて、世界でもアンハイザー・ブッシュとインベブで大規模なM&Aは終わりました。また中国国内でもビック・スリーが固まり、後の会社はファミリービジネスのようなところが多い…。ですから今は緩やかな連携というのか、同じ戦略を共有する連合軍のようなものを作っていくべきではないかと思います。その上で株を持合うような関係を作り、気持ちは通じるようにして何かあったときは支え合おう…、我々がアジアで事業展開する時はそういう繋がりを作っていければと思っています。
|
|
片岡:
|
先年、キリンホールディングスとサントリーホールディングスの統合交渉が持ち上がり、話題となりました。
|
|
池田:
|
話を聞いたときは、これは最初から難しいのではと感じました。勿論、社内ではそれなりに動揺もありましたし、想定して影響や対処法も考えました。もっとも仮に実現しても、脅威となるだけでなく、我々に有利となる面もありました。欧米のように買収と同時にドラスティックなリストラを行い、固定費を減らさないと合弁効果というものはなかなかでませんが、日本の場合はそれができませんので…。また上場企業と非上場ファミリー企業が一緒になろうとするとどうしてもファミリー企業が有利で、サントリーにとっては悪い話は殆どないでしょうが、キリンビールの社員にとっては喜べる状況ではない…。上場企業は最初から企業価値が算定されていますが、ファミリー企業はどんなに厳しいデューデリをしても算定し難い面があります。更に株式交換であれば、どういう比率にしても、ファミリーが筆頭株主になってしまうのは自明の理で、それでは身売りするのと同じ事になってしまいます。米国のように議決権を持たせないような方法もありますが、日本では難しいでしょう。
|
|
片岡:
|
貴重なお話を有難うございました。
|
|
|
~完~
|
|
|
|
|
|
|
|
インタビュー後記
池田さんのキャリアにとって最も大きな出来事は卸会社に出向して成田空港開港を控えた成田地区の支店長に着任、そのエリアの人口増加に伴い売上も急増し、それによって人が成長していくことをそこで初めて実体験できた事だそうです。通常支店では、本社から販売目標が示された時、個々の営業マンが「自分が担当しているこの店は…」と積み上げて出してくる数字を併せ、それだけでは目標に達しないので残りは皆で努力して…となります。しかし急成長していると営業マンが「この地域は人口がこれくらい伸びている、シェアがこの程度だから売上も…」とマクロから見て検証して予算を作るという形に自然と変わっていったそうです。 |
|
|
|
聞き手
片岡 秀太郎
1970年 長崎県生まれ。東京大学工学部卒、大学院修士課程修了。博士課程に在学中、アメリカズカップ・ニッポンチャレンジチームのプロジェクトへの参加を経て、海を愛する夢多き起業家や企業買収家と出会い、その大航海魂に魅せられ起業家を志し、知財問屋
片岡秀太郎商店を設立。 |
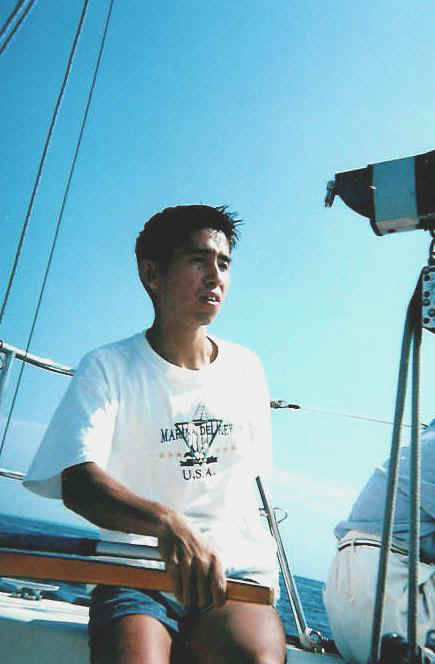 |
|
|
|
|
|
脚注
|
|
|
注1
|
http://ja.wikinews.org/wiki/アメリカのアンハイザー・ブッシュ、インベブによる買収に合意。買収金額は約520億ドルに (最終検索2011年7月28日)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
右脳インタビューへ |